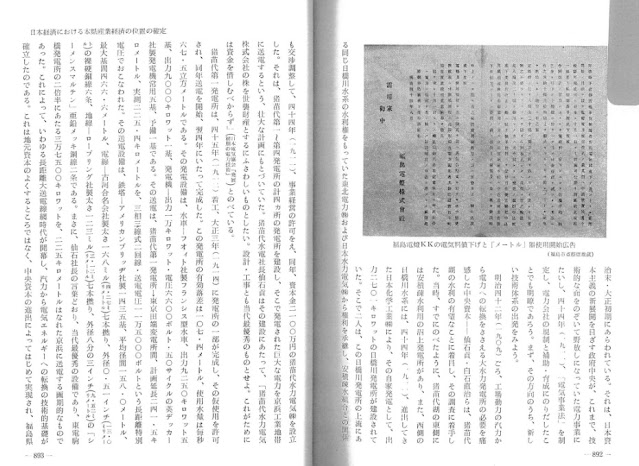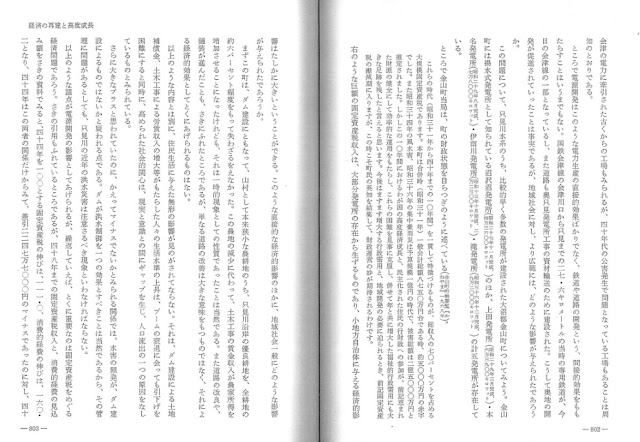■2025年2日7日(金)大雪
※ 昨夜から今朝の新雪は80cm.積雪深は250cm.災害級。各種冬行事は中止 延期。学校も休校。
昼のNHKテレビ。金山町232cm、若松121cmで過去最深と。只見は279cmで今後300cmになる。
■ 7日、午後4時~ 農文協編集部より電話あり。現代農業連載の11月号、12月号記事の送稿内容の確認。
・数日降雪、晴れ・曇りの天候が、2月に変わり、1週間降り続く。只見町の雪祭りもJRの運行停止、道路の通行止め等でキャンセル(宿泊)のニュースがある。
連日、1晩で100cm近く降っている。降った雪は重さで沈むから累積している積雪は思ったより深くないが、昨夜のFTVは白河の西郷村の太陽光発電建設に伴う土砂流出について18時台の報道があり、只見町での3m超えの雪に近づいている、、、近年では360cmの積雪を超えるか?という。昭和村は252cmに。
・小野川本村で役場の農政懇談会が延期になると連絡がある。
・カネヤ産業の菅尾氏からオランダから輸入したローズヒップ試作苗の送付の遅延等について電話がある。京都生花の花絵巻会場にいる、ということだった。2023年秋に注文していたもの。
・昨夜、南会津町南郷の月田農園の礼次郎さんから電話があった。携帯電話・スマートフォンに電話が来るのだが、固定電話はもう使わない時代になっている。ハンズフリーで、スピーカーからの音で話す。
雪が多く、農園にも登れない、、、スノーモービルを使用していた、、、、
・博士トンネル付近の旧道入り口が除雪してあり、休日にそこに駐車してスノーモービルが毎週10台近く集結して旧道走行していたが、入り口が除雪されず、駐車スペースが無くなり、国道脇駐車数台になっている。高田側の進入禁止の旧道のバリケードを外し中に駐車してもいたが、そこも除雪されず駐車できなくなっている。
・今日は、土蔵(くら)の屋根の雪下ろし。今冬初。これまでの年は年に数回下ろした。屋根が空中に設置しているのでトタン屋根でも落ちにくい。それ以外の建物(大型ハウス、小屋類)は晴天時の午前に石油ストーブ(温風)を数台、燃料無くなるまで室内で焚いて、空気を暖め屋根を暖めてトタン屋根の雪を自動落下させている(近年のやり方)。
この冬は気温が高く、大雪の合間の晴れが、土蔵の屋根雪を自落下させていたが、2月は気温低下、通常の冬になって雪は落ちない。
パイプハウス関係も、この2月の雪が2mを超えるようになり、ハウス骨組みが埋まりつつ有り、肩パイプ部分を、かんじきで踏んで低くする、、、スコップで掘る、、、除雪機で雪をのける、、、等が必要になっている。
・16時、農文協から『現代農業』連載原稿の確認の電話協議を予定。先日、2回目の連載である3月号の「洋種ヤマゴボウ」について読まれた方から連絡がある。北海道の人。
■2月6日は、『福島県史』を読む。
第25巻 自然・建設 1965年(昭和40年)
第4巻 通史編 近代1 1971年・昭和46
第5巻 通史編 近代2 1971年・昭和46
第18巻 産業経済1 1970年(昭和45年)
■2月6日、日経 → 洋上風力、日本も冬の時代 三菱商事が522億円損失計上
調達や建設コストの上昇が洋上風力発電の開発を直撃している。三菱商事は6日、2024年4〜12月期の連結決算(国際会計基準)を発表し、国内3海域のプロジェクトで522億円の損失を計上した。コストの膨張で事業の縮小・撤退が相次ぐ米欧の不況の波が日本にも及んだ格好で、国は支援制度の見直しに動いている。
「3年間にわたり開発を進めてきたが、世界的なインフレや円安、地政学リスクに端を発した環境の変化は当初の想定を大きく上回る」。6日の記者会見で三菱商事の中西勝也社長は、能代市沖(秋田県)、由利本荘市沖(同)、銚子市沖(千葉県)の3海域で進める洋上風力プロジェクトの損失の背景についてこう説明した。
24年4〜12月期の連結決算は、純利益が前年同期比19%増の8274億円だった。洋上風力関連の損失計上は利益の押し下げ要因になるが、銅事業などで利益が上振れし、25年3月期通期の業績予想は変えなかった。
28年9月以降に完成を見込む洋上風力事業は遅れや追加損失が懸念される。中西社長は「再評価を進めてゼロベースで検討する。今後の方針は改めて公表する」と述べた。21年末の国の第1弾公募の入札で示した売電価格についてリスク管理の甘さが指摘されるが、「見通しの甘さよりコスト増が要因」と強調した。
洋上風力は設備に数万点の部品が使われ、事業費も大型だと数千億円に達する。事業費の過半を調達や建設のコストが占め、物価高の影響が顕在化しやすい。英BPと洋上風力発電事業の統合を決めたJERAの奥田久栄社長は「インフレの影響がかなり出ている」と指摘。同社によると、風車の調達コストは過去4年で1.5〜1.8倍に上昇した。
世界では欧米を中心に撤退・延期が相次ぎ、米エネルギー情報局(EIA)と国際エネルギー機関(IEA)のデータを集計すると、23年10月からの1年間で影響を受けた事業は出力ベースで約600万キロワットに達した。23年の新規導入量の半分超に当たる。米国や英国、フランスなどの沖合で開発費の増加を理由に大型事業が相次ぎ頓挫した。
洋上風力最大手のデンマーク企業オーステッドは24年10〜12月期に米国事業で121億デンマーククローネ(約2600億円)の減損損失を計上した。英BPやノルウェーの石油大手エクイノールも23年に同国事業で巨額の減損を出している。
日本でも環境の悪化は徐々に顕在化していた。24年12月に国が結果を公表した第3弾の事業者公募では事前調査を実施した企業の約半数が入札を見送った。外資勢でもオーステッドやカナダ電力大手ノースランド・パワーが日本事業の縮小に動く。
第3弾の入札に応札しなかったコスモエネルギーホールディングスの岩井智樹常務執行役員は24年8月の決算記者会見で「まずは陸上風力で足場を固める」と話した。事業者が懸念するのが落札価格の低さだ。安値水準が続き、採算の確保が難しくなっていた。
電気事業連合会の林欣吾会長(中部電力社長)は「国内外で洋上風力発電はビジネスとして非常に厳しい状況だ」と話す。推進には公的支援の強化が不可欠になってきた。
英国は24年の入札から電力販売価格の目安となる上限価格を23年に実施した前回から66%引き上げた。米ニューヨーク州も事業者が過去に落札した事業の開発費などの見直しを認めるなど入札条件を見直した。
足元ではインフレ以外の逆風も吹く。化石燃料への回帰を掲げる米国のトランプ大統領は風力発電を「最も高価なエネルギー」と呼び、土地の貸与など政府支援の縮小に動く。すでにニュージャージー州が新規入札をやめるなど影響が広がっている。世界で普及の動きが鈍化すれば、製造コストの低減も進まない。
日本政府は洋上風力で40年までに3000万キロ〜4500万キロワットの案件を形成する目標を掲げる。24年末に示した次期エネルギー基本計画案でも再生エネの主力電源化への「切り札」と明記して、今後も推進していく姿勢を鮮明にする。
1月には25年度から事業者公募のルールを見直す方針も固めた。上昇した一部コストの電力価格への上乗せ容認や運転開始が遅れた場合のペナルティーに柔軟性を持たせる。2月下旬には関連産業の育成へ支援策などを協議する有識者会議も立ち上げる。
ただ、公的支援は国民負担と隣り合わせだ。米ニューヨーク州は採算が悪化した約300万キロワット分の事業などについて、売電価格を上げて救済すれば家庭の電気代が2%以上上昇すると試算した。英国などは産業振興とセットで支援の妥当性を訴える。
日本は遠浅の海が少ない。大量導入には沖合に風車を浮かべる「浮体式」の導入が欠かせない。建設コストは導入が進む着床式の約2倍とされ、今後は公的支援の重要性がさらに高まる。国民負担へ理解を得るには成功モデルが欠かせなくなる。
三菱商事が損失を計上した3海域は国の第1弾公募の事業で日本の洋上風力を象徴する位置づけだった。その動向が風力業界や電源としての信頼に与える影響は大きい。日本の洋上風力は主力電源化へ正念場を迎えている。
------------
■2月7日、会津盆地の農道を通行したがホワイトアウト(雪でまっしろになり道路が見えなくなる)で自動車が3台、水田に転落していた。